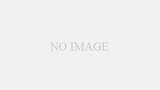〖体験談〗大型二種免許の教習内容・費用・給付金まで徹底解説|バス運転免許のリアル
大型一種・けん引・大特と順番にステップアップしていく中で、
「どうせなら大型二種(バス免許)まで取りきってしまおう」と思うようになりました。
実際にバスを運転する予定があるわけではなかったものの、全車種コンプリートを目指すうえで避けて通れない免許であり、
将来的に仕事の選択肢を広げられる資格だと感じたのが、大型二種にチャレンジしたきっかけです。
この記事では、教育訓練給付金の使い方/教習所選び/教習内容の違い/免許センターでの学科試験/かかった費用まで、
実際に大型二種を取得したときの体験談をベースにまとめました。
なお、事前に
大型一種免許の体験談や
深視力検査の解説、
隘路・路端停車の攻略記事
を読んでおくと、全体像がつかみやすくなります。
はじめに|大型二種を取ろうと思った理由
大型一種 → けん引 → 大特と進んでいく中で、
「どうせここまで来たなら、二種も取ってしまいたい」という気持ちが強くなりました。
大型二種免許があれば、
- 路線バス・観光バス・送迎バスなど人を乗せて運賃をもらう仕事ができる
- 運送系だけでなく、旅客・観光・送迎業界にも仕事の幅が広がる
- 「いつでもドライバーという選択肢を持てる」という安心感が手に入る
さらに、前回の大型一種で
教育訓練給付金制度を使ってお得に免許を取れた経験もあり、
「もう一度あの制度を活用してみたい」という思いも後押しになりました。
まずは教育訓練給付制度の対象か確認するところから
大型二種はどうしても教習料金が高額になりがちです。
そこで最初にやったのが、教育訓練給付制度の利用可否を確認することでした。
条件として代表的なのは、次の2つです。
- 前回の受講開始日以降の雇用保険加入期間が3年以上あること
- 前回の給付金支給日から今回の受講開始日まで3年以上経過していること
「たぶん大丈夫だろう」と思って確認してみたところ、
実際にはあと3か月待たないと対象にならないことが判明(当時:2023年7月)。
そこで、10月入校を目標にスケジュールを調整し、
一般教育訓練(20%)ではなく、当時40%(現在は50%)戻ってくる「特定一般教育訓練給付制度」を利用して通うことに決めました。
教育訓練給付制度の概要や対象者の条件、申請の流れについては、別記事に詳しくまとめています。
▶ 教育訓練給付金でお得に免許を取ろう!
教習所選び|行田自動車教習所を選んだ理由
大型二種を教習している自動車学校は、大型一種よりさらに数が限られます。
私が教習所を選ぶときに重視したのは、次のポイントです。
- 特定一般教育訓練給付金の指定講座になっているか
- 大型二種(バス)の教習車がしっかり用意されているか
- 土日中心でも教習スケジュールが組めるか
- 無理なく通える距離か(それなりに遠くても、リターンが大きければOK)
あちこちの教習所を調べた結果、最終的に選んだのが
行田自動車教習所(埼玉県行田市) です。
自宅からは電車で約2時間弱、クルマでも1時間以上かかる距離でしたが、
特定一般教育訓練給付金の対象講座であること、そして返ってくる金額の大きさを考えると、
多少遠くてもここで取る価値があると判断しました。
給付金対象者として申し込むと、最初に教習の全スケジュールを組んでもらえるのも大きなメリット。
仕事の都合に合わせて土日中心で通いたかったので、非常に助かりました。
教習所選び全般の考え方については、こちらの記事も参考になります。
▶ 教習所選びは「立地と路上コース」で決まる!
教習の内容と印象的だったポイント
大型一種(トラック)と大型二種(バス)の違いにビックリ!
大型二種の教習でまず驚いたのは、車両の構造による感覚の違いでした。
大型一種(トラック)では、前輪タイヤが自分のお尻の真下あたりにありますが、
大型二種(バス)は前輪がかなり後ろ寄りにあり、右左折のときに
「自分の身体だけ先に飛び出していく」ような不思議な感覚になります。
最初はこの“飛び出し感”に戸惑ったものの、実際にはトラックよりホイールベースが短く小回りがきくため、
車庫入れやS字・クランクなどは、感覚さえつかめばむしろ操作しやすいと感じました。
一種と二種での教習内容の違い
課題としては、交差点・方向転換・S字・クランクなど、大型一種と共通するものに加えて、
大型二種では「鋭角(V字コース)」という独特の課題が追加されます。
鋭角は、V字型に折れた狭い通路を大きな車体で通過する課題で、
車体の前後の振り幅・後輪の位置をシビアに把握していないと、すぐに脱輪や接触につながります。
さらに、バスならではのポイントとして
- 電柱や標識などの目印とドア位置を合わせて停車すること
- 発進・停止のたびに乗客を意識したスムーズな操作を行うこと
などが常に求められます。教官からは何度も
「乗客にGを感じさせない運転を!」と念押しされました。
車両感覚の基本は、大型一種の教習や
隘路・路端停車の記事
で鍛えた感覚が土台になっていると感じました。
そして久しぶりの学科教習
大型二種では、学科教習が計19時間あります。
大型一種・けん引・大特には学科がなかったため、久しぶりの教室での座学に少し新鮮さを覚えました。
内容としては、普通免許のときと同じように
- 教官による講義
- 映像教材(ビデオ)の視聴
といった形で1コマずつ進んでいきます。
特に印象に残ったのは、応急救護処置の講習(6時間)です。
人形を使って人工呼吸やAEDの操作を実際に行う中で、
「人を運ぶ免許」ならではの責任の重さを強く意識させられました。
教習スケジュール
教習時間はおおよそ次のような配分でした。
- 第一段階:技能8時間+学科7時間
- 第二段階:技能10時間+学科12時間
大型免許を持っている前提のカリキュラムなので、意外と実際にバスに乗る時間は少なめです。
その中で鋭角コースを体に叩き込む必要があったので、ここが一番苦労したポイントでした。
私の場合、入校式は2023年10月7日、教習スタートが10月22日、
卒業予定日は11月26日というスケジュールを組んでもらいました。
基本はすべて土日で教習を消化し、どうしても合わない学科だけ、
平日に有給休暇を1日だけ取得して通学。結果として、ほぼ予定通りに2か月弱で卒業できました。
免許センターへ|ウルトラ教室という“強い味方”
これまで取得してきた大型一種・大特・けん引では、
免許センターでは書類提出+視力検査+深視力検査で済み、学科試験はありませんでした。
しかし、大型二種は初めての二種免許だったため、免許センターで学科試験を受ける必要があります。
学科試験に合格して、ようやく新しい免許証が交付されます。
私の住む埼玉県の場合、免許センターはかなりアクセスしづらい場所にあり、
行くだけで一大イベントです。
そんな埼玉の免許センター周辺には、他県の人に話すと驚かれる「便利なお店」があります。
それが ウルトラ教室 です。
いろいろ大人の事情はありそうですが、ざっくり言うとこんなサービスです。
- 利用料は普通免許で3,000円、二種は4,500円ほど
- ヘッドフォンがずらっと並んだ部屋に案内される
- ヘッドフォンから運転免許の問題と解答が流れてくる
- その後、免許センターで問題用紙を開くと…「さっき聞いた問題がズラッと並んでいる」
ウルトラ教室はこれまでに3回利用しましたが、
3回とも驚くほど似た問題が出てきたので、
「これはまぐれにしては出来過ぎだな…」という印象です。
学科試験に落ちてもう一度鴻巣まで行くことを考えると、
4,500円で一発合格の確率をグッと上げられるというのは、かなりありがたい存在でした。
結果として、ウルトラ教室のおかげもあり、
学科試験は無事一発合格 → 大型二種免許を取得することができました。
費用の内訳と実際にかかった金額
気になる費用についても、実際の数字を公開しておきます。
- 支払総額:317,900円(入学手続き時に支払った金額)
- うち給付金対象額:309,100円(この金額の40%が給付)
- ハローワークから振り込まれた給付金:123,640円
- 実質負担額:194,260円
教習はオーバーも補習もなく、すべて一発合格だったため、追加費用は発生していません。
大型二種はどうしても高額になりがちな免許ですが、
教育訓練給付制度を活用することでここまで負担を下げることができます。
まとめ|これから大型二種免許を取る人へ一言
大型二種は「難しそう」「お金がかかりそう」と構えてしまいがちな免許ですが、
実際に取ってみると、
大型車との感覚の違いさえ早めに押さえれば、そこまで極端に難しいわけではないと感じました。
特にポイントになるのは、
- バス特有の車両感覚(前輪位置・オーバーハング)に慣れること
- 鋭角コースをYoutube動画なども活用しつつイメトレしておくこと
- 深視力検査や
隘路・路端停車など、大型免許共通の難所を事前に研究しておくこと - 教育訓練給付制度をフル活用して、経済的なハードルを下げること
これから大型二種にチャレンジしようとしている方は、
ぜひ以下の記事もあわせて読んでみてください。
大型二種は、運転技術・安全意識・応急救護の知識まで含めて自分をレベルアップさせてくれる免許です。
興味がある方は、ぜひ一歩踏み出してみてください。